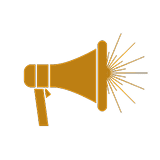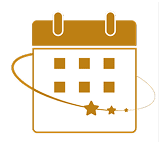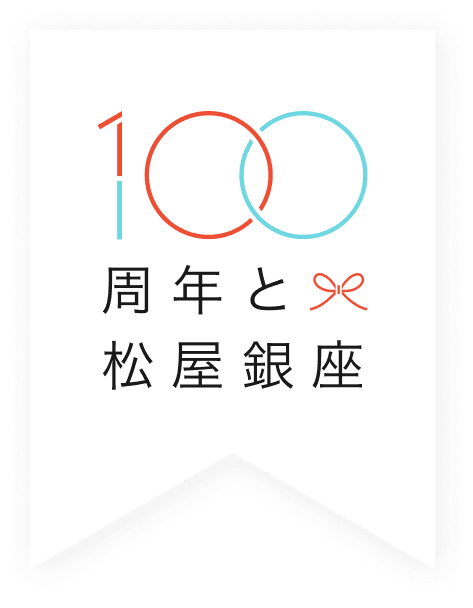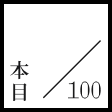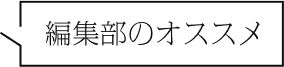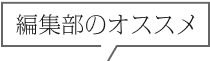明治から大正、昭和初期、日本にまだ美術館や博物館、文化施設が少なかった時代、美術愛好家にとって百貨店の文化催事は貴重な存在でした。松屋では、今川橋・松屋呉服店時代から展覧会を開催した実績を持ち、1910年に『扇子展覧会』を行った記録が残っています。1925年(大正14年)には、銀座店の開店記念『今様風俗人形陳列会』が催されました。
現在は8階イベントスクエアで、年間約28万人が来場。“松屋の展覧会”として注目を集めるその舞台裏を探るべく、企画から空間づくり、グッズ、運営まで担うコンテンツ事業部の下山郁恵さんに、設営中の会場でお話を伺いました。
自分たちで考えたオリジナルの企画を販売する業態へと進化

――100年続く展覧会の歴史の中では、いくつものターニングポイントがあったと思います。現在の松屋銀座の展覧会はどのような体制で運営されていて、そこに至るまでにはどんな変化があったのでしょうか?
「近年では、2013年に『文化催事課』から『コンテンツ事業課』へ、2016年には『コンテンツ事業部』へと名称が変わりました。
コンテンツ事業部になったときに大きく変わったことは、私たちが企画した展覧会を松屋銀座の会場だけで終わらせるのではなく、全国の美術館や他の百貨店に販売する形になったことです。作品の権利元や先生方から展覧会の開催について許可をいただき、松屋発のオリジナル展覧会を、全国へ届けることができるようになったんです。
また、展覧会グッズの販売体制も変わりました。
それまで、グッズ販売は売り場が主導だったんですね。例えば絵本展だとおもちゃ売り場、絵画展や写真展だと美術売り場が物販を担当していました。でも展覧会とグッズは切り離せないものということで、このときから企画から物販までを一貫して手がける体制になりました」
――自分たちで企画した展覧会を外部に販売するようになったということですが、以前はどのような形だったのでしょうか?
「それまでは、ほかの会社と共に松屋銀座の会場のみで展示をする、ということをずっとやっていました。会期中はずっと会場に立って、お客様がどういう展示に興味を持つのかを見ながら、『松屋としてこういう展示にしたい』『お客様が興味を持つテーマは何?』ということを考えてきたんです。
先輩たちのそうした積み重ねが、展覧会を企画できるスキルに繋がり、今では自分たちで作った展覧会を、松屋銀座だけでなく全国の会場に展開するという現在の体制につながっているのだと思います」
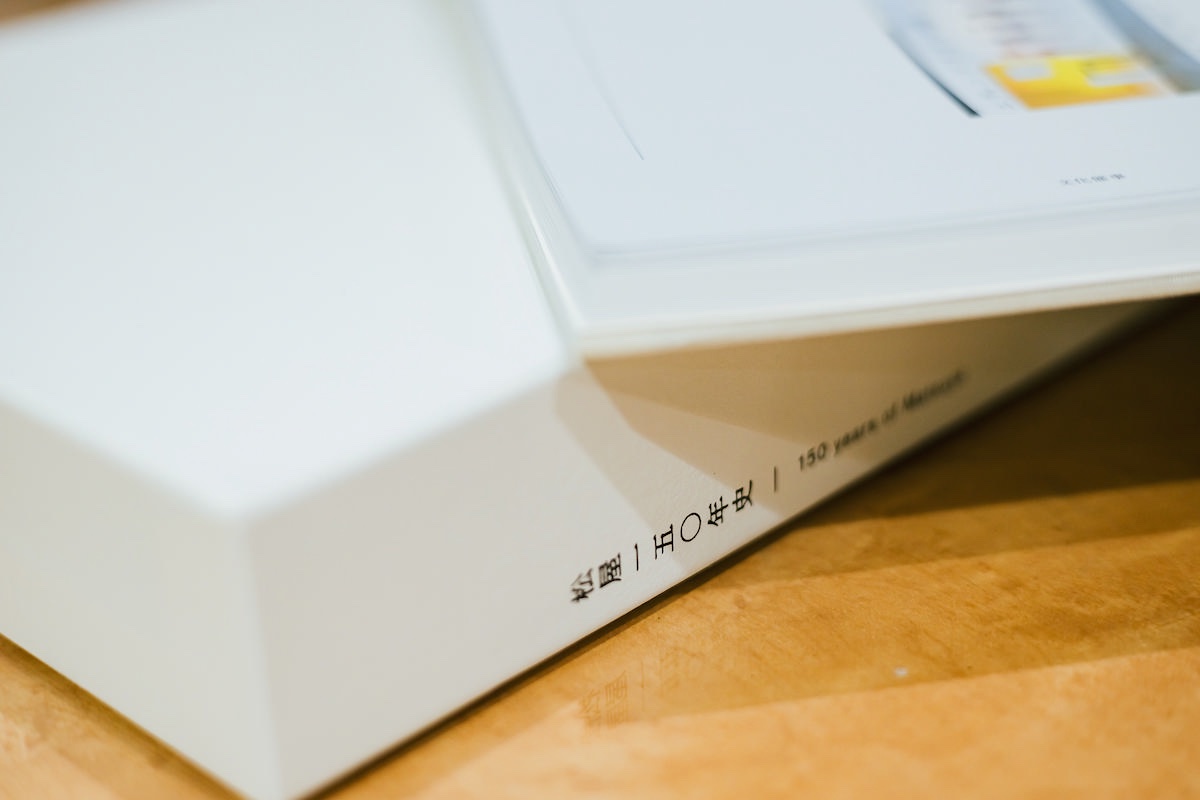
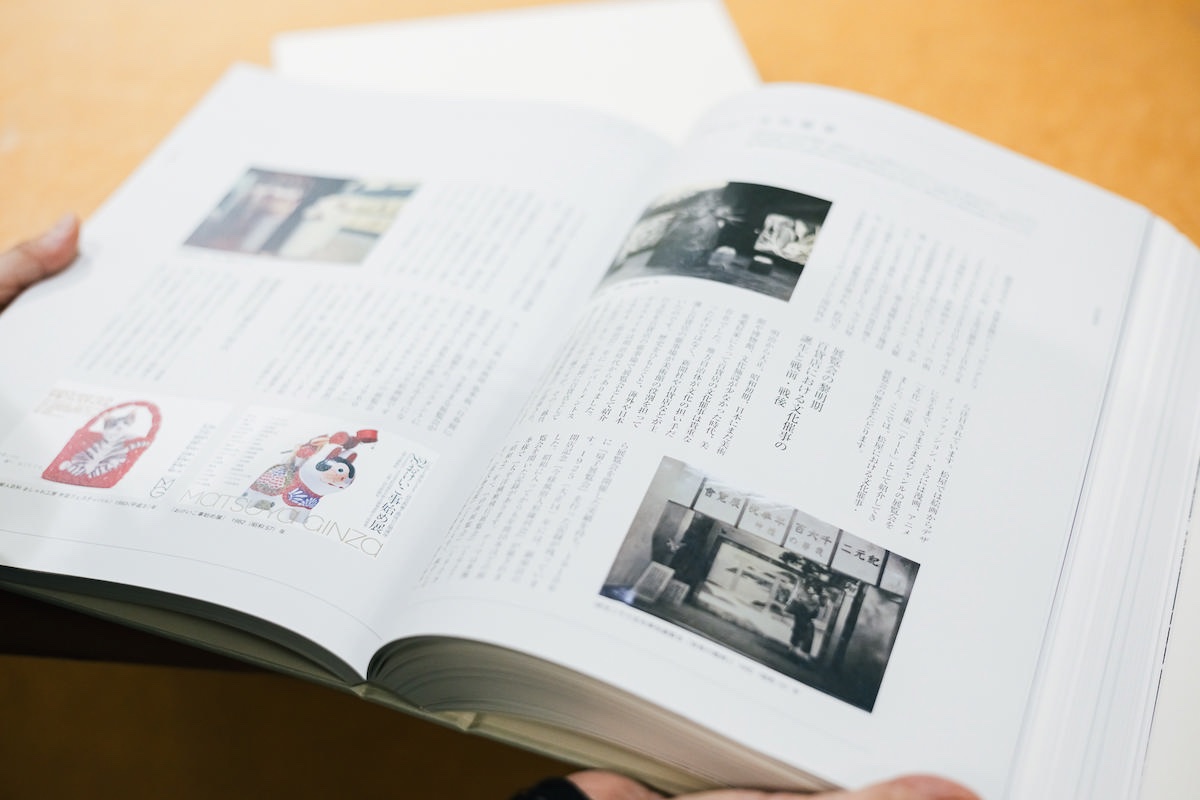
――松屋銀座にとって、展覧会はどんな役割を担っていると思いますか?
「ひとつは、まだ松屋銀座を知らない方や、知っていても訪れたことのない方に対して、足を運んでいただけるきっかけを作ること。もうひとつの役割としては、“買い物”以外の体験を通して、松屋銀座で一日中楽しんでもらうことだと思っています」
楽しんでいただくために“松屋らしい”企画内容を考え続ける
――展覧会を企画するにあたって大切にしていることがあったら聞かせてください。
「どんな新しい企画なら松屋に来てくださるお客様が楽しんでいただけるのか、どういう宣伝をすればお客様に知っていただけるのか、ということを考え続けることです。ストレスなくまわっていただくための導線設計や当日の運営も、ですね」
――企画が決まってからはいかがですか?
「コンテンツを生み出している先生や制作委員会の皆様は作品に魂を込めています。なので、それを展覧会というリアルな場所でいかに楽しんでいただけるか、です。作品やファンについては、先生や制作委員会の方々のほうが当然詳しい。その上で私たちは展覧会のプロとして、どういう見せ方にしたらファンの方に喜んでもらえるのかを毎回考えます。
自分たちだけで勝手に作るのではなく、先生やアニメーションを作っている方と何度もお話をして、コミュニケーションを取りながら、一緒に作っていくことをすごく大事にしています」


――展覧会を開催する作品は毎回どうやって選んでいるのでしょうか。
「基本的に、コンテンツ事業部の担当者が『こういう展覧会がやりたい』と部内のミーティングで提案をするところから始まります。提案したものが100%できるわけではなく、そこから作品の権利元にお話をしに行きます。その過程で、できるかできないかをコンテンツ事業部の中で議論して、顧客販促部とも目線を合わせながら決めています」
――“松屋銀座らしい展覧会”という判断基準はありますか?

「“これは松屋っぽいよね”“これは松屋っぽくないよね”というものが明確にあるのですが、それを言語化するのが難しいんですよね(笑)。
でも、その“らしさ”を誰かがひとりで決めるのではなく、チームで話し合いながら進めているので、“松屋らしい”というイメージの共有はしっかりできていると思います」

100年前から目的は変えず、手段を変えながら作っていく
――展覧会の準備は会期の1年~1年半前から始まると伺いました。そこから開催までの流れを教えてください。
「まずは企画書を作るところからスタートして、それをもとに展示、商品開発、宣伝という大きな枠の中でそれぞれ細かい計画を立てていきます。そこから開催に至るまで、関係各所と打ち合わせをして内容を決めていく、という流れですね。
展覧会を作って終わりではありません。実際にお客様がどんな反応をするのかを常に見て、会期中でも必要であれば手直しをして、よりよいものにしていく。反省があれば次回に生かす、ということをしています」

――設営の様子を見て、チーム感ができあがっていると感じました。
「展覧会を作るチームの皆さんと話していると、“これは絶対にいい展覧会になる!”と思う瞬間があるんですよね。それぞれの得意分野のアイデアがひとつにまとまったときとか、『私もそれがいいと思ってた!』『そうだよね!』というときとか。毎回時間がなくて、“本当に間に合うのだろうか?” と思わない展覧会がないくらいなんですけど…(苦笑)。
それでも粘って進めているうちに、“ああ、これでうまくいく!”と思える瞬間があります。そういう展覧会は、結果的にお客様がたくさん来てくださるんです」

キャラクターの目をプリントしたアイマスクもそのひとつ。
――今後、松屋の展覧会をどのように進化させていきたいですか?
「文化催事を立ち上げた諸先輩方から、受け継がれてきたものの積み重ねなのかなと思っています。
その時代時代の情報を集めて、柔軟に考えながらも、松屋としてお客様にご満足いただけるクオリティの展覧会を作ることは今も昔も変わらないので、“このまま”を続けていきたいですね。
扱うジャンルが、日本画・洋画・工芸といった伝統文化中心から漫画やアニメ、キャラクターが多くなったのも、時代とともに自然とそうなったのだと思います。100年前に開催した展覧会のときから目的は変えずに、それを達成する手段方法を変えながら、今後もいろんな方々と一緒に展覧会を作っていきたいですね」
うらがわ 編集後記
取材中も常に会場の様子に目を配っていた下山さん。普段から心がけていることを聞くと「課内のメンバーみんなに『ほかの展覧会やコンサート、イベントをいっぱい見に行こう!』と言っています。実際に文化に触れることで、自分たちの気付きになることが多いので。体験することが次の展覧会に繋がると思っています」と話してくださいました。
近日開催予定の催事
誕生70周年記念 ミッフィー展
会期:2025年4月23日(水)ー5月12日(月)
会場:松屋銀座8階イベントスクエア
イベント詳細はこちら
PHOTO/AYUMI OOSAKI TEXT/AKIKO ICHIKAWA