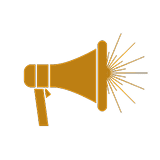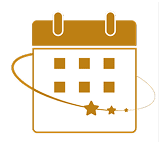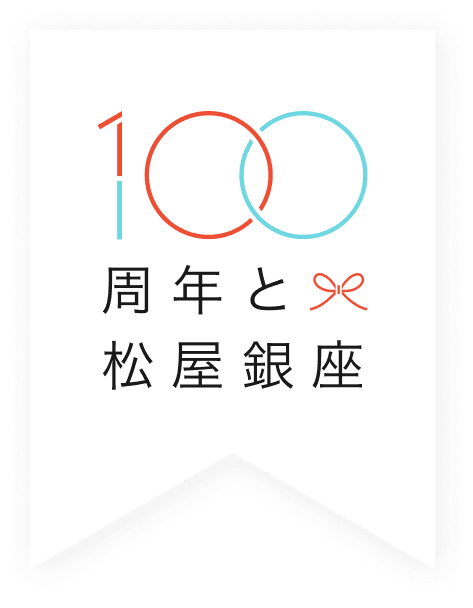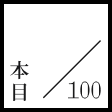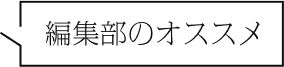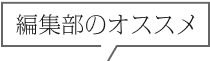松屋銀座開店100周年を記念して、フランスの名門シャンパーニュ・メゾンとのコラボレーションが実現。松屋銀座だけの特別なシャンパーニュ「パイパー・エドシック エッセンシエル バイ マツヤギンザ」が誕生しました。開発責任者であり、ソムリエの資格を持つ和洋酒担当バイヤーの関戸恵実さんに、“松屋らしい味わい”ができあがるまでの過程と、そこに込めた想いを伺います。
「シャンパーニュ」とは
フランスの北東部にあるシャンパーニュ地方で栽培された認定品種(主な品種はシャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエの3種)のぶどうを使って造られるスパークリングワインのこと。醸造や瓶内二次発酵、熟成期間など、厳格な規定の製法で造られたスパークリングワインのみが「シャンパーニュ」を名乗ることができます。
“松屋銀座らしい味わい”を表現するためにこだわったこと

――まずは、今回の企画がスタートした経緯を聞かせてください。
「100周年ということで、“今までにない何か特別なものを作ろう”というところから話がスタートしました。私自身シャンパーニュが大好きということもあって、お取り組みをさせていただいている輸入業者さんにご縁をつないでいただいたんです。
元々、パイパー・エドシックのシャンパーニュは、松屋銀座の地下1階のグルマルシェ・ヴァンで販売されていて、非常に人気があります。カンヌ国際映画祭公式シャンパーニュを務めていましたし、“マリリン・モンローに愛されたシャンパーニュ”としても知られています。そんな華やかなメゾンと共に松屋銀座開店100周年の祝祭感が伝わる商品を作りたいという気持ちからコラボレーションが実現しました」

――どんなシャンパーニュを目指したのでしょうか。
「イメージしていたのは、ご自宅用にもご贈答用にも使えて、幅広いお客様に楽しんでいただきたいということですね。どんな方にプレゼントしても喜ばれるよう飛び抜け過ぎず、でも凡庸ではありたくない。松屋銀座らしいシャンパーニュにしたいと思いました」
――関戸さんが考える“松屋銀座らしい味わい”とは?
「実際にフランスのパイパー・エドシック社を訪れてテイスティングしながら、“どういう味が松屋らしいのだろう?”と考えました。そして、たどり着いたのが、熟成感と呼ばれる、時が作り出す複雑味や奥行きのある味わいと、いきいきとした果実のフレッシュさがお互いの良いところをバランスよく表現しあう味わいです。そこに伝統と革新が入り交り、融合した銀座の街をイメージしました。
また気張った感じがなく、洗練された雰囲気の松屋のお客様や、親しみやすくて、でもちょっとこだわりが強めな“松屋人”たちも頭に浮かびました。そんなイメージに合うシャンパーニュを作りたいという思いが徐々に固まってきました。

それから、私の中でのおいしいワインの定義のひとつは、ワインを飲みこんだ後の余韻の長さと心地よさなんです。ただ飲み物としておいしいだけではなくて、このシャンパーニュを飲んでいただくことがひとつの体験として心に留まるような味わいにこだわりました」
――シャンパーニュの中には甘辛の味わいによって分類があるそうですね。
「シャンパーニュは製造工程の最後に『ドサージュ(補糖)』をして甘味の調整と最後の味付けを行います。1Lあたりに糖分を何g入れるかによって、呼称が変わってくるんです。
今回の松屋銀座別注を製造した『パイパー・エドシック エッセンシエル』というシリーズは“エクストラブリュット”(6g/Lまで)という超辛口のカテゴリーに分類されます。一般に販売されているパイパー・エドシック エッセンシエルの既成品は4gで、松屋銀座別注商品は6gのドサージュになっています。
ちなみにシャンパーニュで最も多くつくられている“ブリュット”(辛口)は12gまでのドサージュなので、エッセンシエル バイ マツヤギンザは超辛口と辛口のちょうど間くらいです」
飲んだ後も口の中で続く“やさしい余韻の長さ”が選定の決め手に
――訪れたパイパー・エドシック社で、関戸さんがどのようにシャンパーニュ作りを進めていったのかを聞かせてください。
「シャンパーニュのぶどうにとって素晴らしい年だった2018年のワインをベースにして、2次発酵を終えたシャンパーニュはデゴルジュマンと呼ばれる澱(おり)抜きの後に先ほど申し上げた「ドサージュ」を行います。今回はこの「ドサージュ」で補糖するグラム数と、最後の味付けとしてブレンドする熟成されたリザーヴワインを選定しました。
リザーヴワインはシェフ・ド・カーヴ(最高醸造責任者)のエミリヤン・ブティヤ氏に4種類のリザーヴワインをご用意いただきました。シャルドネ100%、ピノ・ノワール100%、ムニエ100%、そして、シャルドネとピノ・ノワールをブレンドし、毎年継ぎ足しながら熟成させているパーペチュアルリザーヴと呼ばれる特別なワインです。
パーペチュアルリザーヴはパイパー・エドシック社ではシェリーの造り方になぞらえて『ソレラ』と呼ばれているのですが、70年代から毎年継ぎ足している、いわば『秘伝のタレ』のような存在なんです」
――その4種類の組み合わせから、選定していくんですね。
「まずは4種類のリザーヴワインを単体でテイスティングし、それぞれの特徴を確認しました。次に、それらをベースワインにブレンドし、ドサージュ(補糖)3gと6gの2パターンずつ、計8種類をブラインドでテイスティングしました」


――その過程を経て関戸さんが選んだものは?
「ドサージュの違いに関しては、すぐに6gにしようと決まりました。お客様が飲まれるシチュエーションを想像したときに、お食事のシーンが多いと思ったんですね。ドサージュがほどよくされていると味わいにふくらみが出て、ぺアリングできるお食事の幅が広がるんです。たとえば、淡白なサラダやカルパッチョだけでなく、軽めのお肉料理や中華料理など少し味が濃いお料理とも合わせやすいです。それからスイーツとのマリアージュも楽しめますね」
――そこからリザーブワインの選定ですね。
「最終的にドサージュ6gのシャルドネ100%、ピノ・ノワール100%、ソレラの3種類に絞りました。(この時点ではまだそれぞれがどのリザ―ヴワインだったのかは知りません)それぞれのワインに個性があるので、その中でどれが松屋銀座100周年にふさわしいのか、すごく迷いましたけど、最後に私が選んだのは『ソレラ』でした」

――最終的な選定のポイントは?
「『ソレラ』はまず口に入れる前の香りがすごくよかったです。飲む前から期待感が高まりました。味わいは果実味のボリュームが感じられるけど、重すぎず、フレッシュさもあって。そこに熟成ワインの複雑味が追ってきて、最後に飲み込んだ後も細く、やさしい、おいしい余韻がずっと続いたんです。余韻の長さや心地よさは『ソレラ』をブレンドしたものが断トツで、最後の決め手はそこでした。親しみやすいのだけれど、“ただのいい人(ワイン)”で終わらずなぜか忘れられない、また会いたくなる。作りたかったシャンパーニュにぴったりでした」
温度による味わいの変化や経年による熟成を楽しんでもらえたら
――その後、実際にフランスから到着したシャンパーニュを飲んだときの感想を聞かせてください。
「“おいしいシャンパーニュができた!”と非常にホッとしました。同時に、みなさんに召し上がっていただきたい気持ちになりましたね。お客様に自信を持ってお勧めできるシャンパーニュになったと思います。
8つの選択肢から選んだときにこだわった、香り、フレッシュさと熟成感のバランス、余韻の長さ……そのどれもがしっかりと感じられました。テイスティングを行ったのは8月、実際に販売するシャンパーニュのデゴルジュマンとドサージュを行ったのは9月ですので、多少熟成されたことで果実味やボリュームもきれいに表れています。
口に含んだ時の第一印象が果実のおいしさをダイレクトに感じていただけるシャンパーニュになっていて、ご自宅用としてもご贈答用としても、シーンや『これに合わせて』ということを気にせずにお召し上がりいただけるかと思います」


――このシャンパーニュをどういうふうに楽しんでいただきたいですか?
「まず、あまり難しく考えず、気軽に楽しんでいただきたいですね。
実際にボトリングされたものを飲んでみて、温度の変化によって味わいの印象が少し変わるのが、おもしろいと感じました。最初はしっかり冷やしてフレッシュ感や酸味を楽しんでいただいて。その後は冷やさずに少し置いて温度が上がった状態で2杯目、3杯目を。そうすると熟成感や丸みをより感じられると思います」


――1本のボトルで印象の違いを体験できるのは、おもしろいですね。
「ほかにも楽しみ方があります。このシャンパーニュは、今飲んでおいしいですが、寝かせておくことで熟成が進み、また違った味わいになります。開けたてのフレッシュさもいいですし、時を経て円熟した味わいになっていくのも楽しみのひとつです。
実はおいしいシャンパーニュって、泡が抜けた後でも純粋なワインとして味わい深いんですよ。そんな小さなロマンも楽しんでいただきたいですね」
パイパー・エドシック エッセンシエル バイ マツヤギンザ(750mL)11000円

発売日:2025年5月1日(木) ※2500本限定
売場:地下1階グルマルシェ ヴァン
※松屋オンラインストアでは2025年5月1日(木)午前11時発売開始
PHOTO/NORIKO YONEYAMA TEXT/AKIKO ICHIKAWA