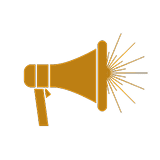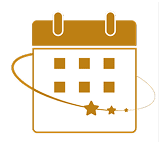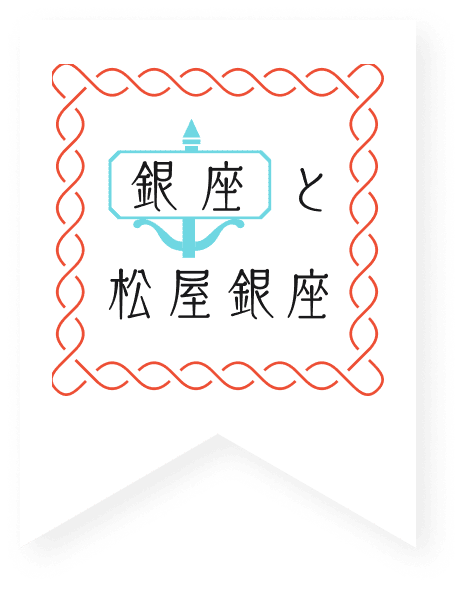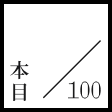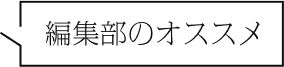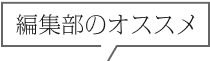銀座で営みを続ける「名店の若旦那・若女将」にナビゲーターとして登場していただき、銀座の街の魅力から長年紡いできたお店の歴史をインタビュー。若旦那・若女将がつながるお店・場所などもお聞きしたので、銀座街歩きも楽しんでみたい。第6回は、100年以上続く看板商品「冨貴寄(ふきよせ)」を再ブレイクさせた、江戸和菓子屋「銀座 菊廼舎(ぎんざきくのや)」の5代目・井田裕二さんにお話をお伺いします。

若旦那
銀座 菊廼舎
5代目
井田裕二さん
PROFILE
1975年東京生まれ。大学卒業後、「銀座 菊廼舎」に入社。8年間家業に従事した後、一度退職し、システムエンジニアとしてIT企業に勤務。2011年「銀座 菊廼舎」に復職し専務取締役、2014年代表取締役に就任した。前職の経験を活かしたネット販売が好評
誕生から100年余り、アップデートし続ける江戸和菓子「冨貴寄」
富や幸せを引き寄せる」の願い込めたお菓子
目にも楽しい、色とりどりの千菓子が詰まった「冨貴寄(ふきよせ)」で知られる江戸和菓子屋「銀座菊廼舎」。創業は1890(明治23)年、現在の歌舞伎座の前で、初代・井田銀次郎氏が歌舞伎せんべいを販売したの始まりです。
2代目が1920(大正9)年、一度にいろいろな味を楽しめるようにと、全国の郷土菓子を集めて考案したのが「冨貴寄」。初期の頃は壺やガラス瓶に入れて販売していたそう。


「現在まで続くブリキ缶のデザインを考案したの3代目の私の祖父。戦争で一時期店を休業していましたが、1948(昭和23)年に再開し、高度成長期の繁栄とともに、「冨貴寄」も広く認知されていきました」と語るのは、5代目の井田裕二さん。
「一般的には「吹き寄せ」と書きますが、「銀座菊廼舎」では「富や幸せを引き寄せる」の願いを込めて「冨貴寄」と命名しています。縁起のいいお菓子なのでお祝い事にはかかせません」

創業の地で「心安らぐおいしいもの」という先代の言葉を胸に
井田さんが5代目として店を受け継いだのは2011年。時代の流れに抗えず、店舗の売り上げが縮小していたこの年、「会社を閉業するかもしれない」という先代である父の言葉に覚悟を決め、復職しました。まず、季節ごとに楽しめる鮮やかな「冨貴寄」へと一新したことで話題が再燃。IT企業での経験を活かし、ネット販売を強化したことで売り上げ大幅に向上させました。
1971年に銀座コアビルの開業とともに構えていた本店を、2021年、創業の地であるあづま通りに移転。製造の効率化を図るため、同年、千葉に「冨貴寄」製造のための工場も新設しました。
「小さくてもできることからコツコツやることがいちばんの近道」と語る5代目。「心安らぐおいしいもの」という先代の言葉を胸に刻み、いい材料を使うことはもちろん、工場の機械化が進んだ分、“丁寧に仕事をすること”を大切にしています」


本店は銀座で唯一の石畳が敷かれた趣のあるあづま通りに。このあたりは着物関連の店舗が多く、今もなお画廊や喫茶店など歴史あるお店が点在します。銀座 菊廼舎も店内には135年の歴史が感じられるアイテムが展示されています。なかでも目を引くのが、干菓子や落雁、金平糖など「冨貴寄」を作る際に使用されてきた木型。

「カウンターに展示しているのは、3代目が1950年代頃に使用していたもの。カラフルなお菓子を作る際に使われ、美しいデザインの『冨貴寄』を生み出してきた大切な道具です。現在は機械がメインですが、富士山モチーフの菓子など、特注の菓子作りには今も木型が活躍しています」

銀座の街にふさわしい、上品で華やかな「冨貴寄」
いまや来店客の9割が求めるという、5代目の手でさらに美しく進化を遂げた「冨貴寄」。バターを使用せず小麦粉と砂糖と卵のみで作られた和風クッキーの上には、カラフルな金平糖や日本の四季を表現した和三盆をはじめ、落雁、黒豆、ピーナッツ、結び寒天など20~30種類、色違いを含めると40~50種類の干菓子が隙間なく詰め込まれています。

「リニューアルする際には、“銀座らしさ”を表現できればとデザイン性も重視しました。玉手箱を開けるように、缶を開けた瞬間のワクワク感を楽しんでいただけたら嬉しいです。秋には月うさぎやハロウィンなど季節限定の菓子を揃え、日本ならではの四季の趣をお届けしています。また今年はミニチュア冨貴寄キーホルダーのノベルティも作りました」


銀座の工房で和菓子職人が作る季節の生菓子も


「銀座 菊廼舎本店」では、併設する工房で和菓子職人が作る四季折々の生菓子にも出会えます。 あづま通りの現店舗を開店した際に、店内厨房で作るようにしました。
ガラス越しに、生粋の和菓子職人による和菓子作りの様子を眺められるのも貴重な体験。
精巧な職人技が光る生菓子。10月から11月は栗きんとん、年末年始は、お正月の縁起物と言われる花びら餅が登場。 季節の練マカデミアナッツと江戸和菓子のマリアージュが楽しめる揚げまんじゅうも人気の菓子です。
販売員との会話を楽しみに訪れる常連客も多いという「銀座 菊廼舎 本店」。雲平という千菓子に「おめでとう」や「ありがとう」などのメッセージ(1枚110円)を印字して、大切な方へオリジナルギフトを贈るのも素敵です。
若旦那・井田裕二さんとつながる銀座さんぽ
「美しい街並みと商品やメニューへのこだわり・・・街を愛してやまない商人が集まっているのが銀座の魅力ではないでしょうか。路地裏文化のある銀座は、隠れた名店も多数。大正時代創業の中華そば屋や餃子の名店など、ランチはとくに良心的な価格でお腹も心も満たしてくれます」 (井田さん)
種類豊富な揚げたての串揚げが楽しめる「ぎんざ磯むら」
銀座4丁目の街並みを見下ろす空間で40年以上親しまれる串揚げ専門店。常時30種類以上、年間100種類以上の串揚げが味わえます。旬の素材を秘伝のねりやと特製の細目のパン粉をつけ、数種類のブレンド油で揚げることでふわっと香ばしい串揚げに。

「中高校時代の同級生が営む店ということもあり、ランチで利用しています。鮮度のよさを感じる太くて長いホクホク食感のアスパラバスや、餅と明太子などの変わり種など種類が豊富で飽きずに楽しめます。ランチタイムは、ご飯や味噌汁がおかわり自由 なのも気に入っています」(井田さん)


〈串揚げ〉ぎんざ磯むら 銀座四丁目店

TEL.03(3571)2564
住所/中央区銀座5-8-17 ギンザプラザ58 6F
営業時間/ランチ午前11時30分~午後2時30分(L.O.午後2時) ディナー午後5時~午後10時(L.O.午後9時)
定休日/月(祝の場合は翌火休)
アクセス/銀座駅より徒歩1分
ぎんざ磯むら 銀座四丁目店HP
予約必須!半月型のどら焼きひと筋「木挽町よしや」
半月形のどら焼きで知られる、歌舞伎座の裏手にある創業100年超えの和菓子屋。
初代が、「役者さんの紅を塗った口に運ぶなら小ぶりの方がいいだろ」と一枚の皮を半分にした半月形のどら焼きを考案し、2代目が刻印できる「オリジナルのマイ焼印」を始めたことで20年以上のロングセラーに。
甘さ控えめの餡とハチミツを加えたしっとりやわらかな皮のバランスが絶妙。一週間前からLINEまたは電話で予約が可能です。


「祖父の代からお世話になっているお店で、現店主の中村さんには、父の代に『冨貴寄』の製造にも尽力していただきました。看板商品の『どら焼き』はもちろん美味しいのですが、今は提供休止中の練り切りの美しさはまさに職人技。時々、うちの生菓子を持参して評価を仰いでいるんですよ」(井田さん)



〈和菓子〉木挽町よしや

TEL. 03(3541)9405
住所/東京都中央区銀座3-12-9
営業時間/午前10時~午後3時
定休日/日・祝、土不定休
アクセス/東銀座駅より徒歩2分
木挽町よしやHP
木挽町よしやLINE(予約はLINEで受付中)
今回訪ねた老舗
PHOTO/KAZUHITO MIURA、YUKO CHIBA TEXT/NAOMI TERAKAWA