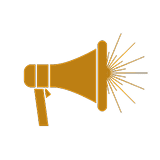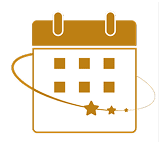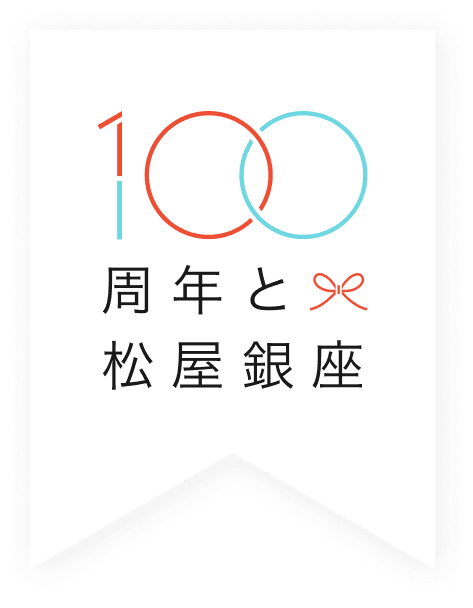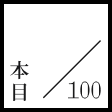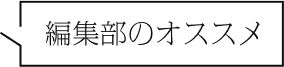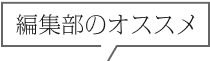松屋銀座の屋上に、緑化空間があるのをご存じですか? 限られた空間でありながら、さまざまな植物が植えられ、訪れるお客様の憩いの場になっています。ここで育てられた植物は商品やワークショップにも活用されており、なかでも、和紙の原料となる「コウゾ」を使った紙漉きワークショップは、親子で参加できるとあって大人気。今回は、松屋銀座の屋上緑化の取り組みとともに、ワークショップの講師をつとめる和紙職人ロギール・アウテンボーガルトさんに、和紙の魅力や子どもたちに伝えたい想いについて伺いました。
都会のど真ん中に緑の癒し。「銀座グリーンプロジェクト」とは?

2007年、松屋銀座の社員有志によって立ち上げられた「銀座グリーンプロジェクト」は、今年で19年目。きっかけは、2006年にスタートした銀座のビルの屋上で養蜂を行う「銀座ミツバチプロジェクト」です。ミツバチのための蜜源をつくろうと、松屋銀座でも屋上に植物を植え始めました。
この緑化空間には、さまざまな植物が植えられています。和紙の原料となるコウゾのほか、コットンや茶葉、さつまいも、レモンなど。普段、都会の街中では見かけない、珍しい植物が多いようです。
三好さん「松屋銀座の屋上にある植物は、単に緑化のためだけではなくミツバチの蜜源としての役割があり、さらに、銀座の街や人々との“つながり”を体現しています」


例えば、和紙の原料である「コウゾ」は、紙漉きのワークショップに活用され、「コットン」は種まきや収穫体験のワークショップに。さつまいもは、「銀座芋人」という芋焼酎になって松屋銀座の地下1階和洋酒売場でも販売中。全国の「芋人」の参加団体が栽培している芋の大きさを競う「イモリンピック」にも出品予定です。
また、「銀座のお茶プロジェクト」に参加し、お茶の葉も栽培しています。銀座で毎年10月に開催される「銀茶会」と連動し、松屋銀座でも「番茶」や「葉茶」をテーマにしたイベントが同月に開催されます。さらに、昨年から育てているレモンの樹木にも実がなり始め、今後はこのレモンを使った商品化も考えているのだとか。
また、季節の花も彩りを加えてくれます。さつまいもが秋冬のオフシーズンを迎えると、そこに今度は菜の花を植える予定だそう。できるだけ一年中、何かしらの植物が楽しめるように工夫が凝らされています。

三好さん「お客様、そして銀座の街があってこそ、私たち松屋銀座は成り立っています。銀座で100周年を迎えられたというのは、みなさまとの“つながり”があってこそ。今後も、そのつながりを大切にしていくために、このような緑あふれる屋上空間を憩いの場として提供したり、定期的にワークショップを開催する場所として、今後も活用していきたいと思っています」
松屋銀座の社員が日々支える屋上緑化。お客様との触れ合いの場にも

屋上緑化の手入れは、松屋銀座社員の三好さんと櫛引さんが行っています。朝、出勤してくると、営業が始まる前までにひと通りの手入れを終わらせているそうです。
夏の時期、一番大事な作業が水やりです。日射しが強くなってしまうと、水やりをやってもかえって植物がダメになってしまうので、できるだけ早い時間に行うようにしています。逆に冬場は、陽がかげる前の日中に水やりを行うなど時間帯にも工夫をしています。


水やりのほかにも、植物の枝や葉に発生する虫を取り除く作業や、雑草取りもできるだけ毎日行います。特にお茶の場合、カイガラムシを放置してしまうと枯れてしまうことも。枝を見回って、白い小さな点々があったら、スコップや歯ブラシで取り除いていきます。

営業時間に植物の手入れ作業をしていると、お客様から声をかけられることもあるそうです。
櫛引さん「『何を育てているの?』とよく聞かれるので、育てている植物についてお伝えすると、そこからワークショップの話につながったり、『地下でこんな商品として売られているんですよ』という話になったり。このようなやり取りは、お客様と社員が“販売”を介さずに気軽に話せるフラットなコミュニケーションになっていると思います。それが、すごく素敵だなと思うんです」
屋上緑化の手入れを担当し始めてからまだ数カ月という櫛引さんですが、普段の仕事とはまた違った、やりがいや魅力を感じていると言います。
櫛引さん「5月ごろにレモンの花、夏前にはコットンの花が咲きます。花がしおれると綿になり、まるで理科の授業のように、植物の成長過程が見られるのは楽しいです。コットンに関しては、今回は種まきから参加することができたので、植物が成長して、その材料がワークショップで使われ、最後にお客様にどんな形で届けられるかを見られることが楽しみですね。育てている植物に、すごく愛着も感じます」
コウゾと和紙でつなぐ未来。和紙職人・ロギールさんの想いとは

和紙の原料となるコウゾやミツマタの一大産地・高知県の梼原(ゆすはら)町を拠点に活動するのが、和紙職人のロギール・アウテンボーガルトさんです。若き頃、オランダのアムステルダムで美術を学び、その後は製本の仕事に携わる中で和紙と出会いました。
ロギールさん「和紙を初めて見たとき、『こんなに美しいものを見たことがない!』と衝撃を受けました。光にかざして透かして見たとき、半透明の紙の中には、繊維などの材料や道具の跡も見えて、それがすごく神秘的な世界だった。教会のステンドグラスも光を透かして楽しむものですが、それと同じ印象でした」
当時(1979年)、和紙に関する情報はほとんどなく、自ら調べ始め、3〜4カ月後には来日。約5ヶ月かけて全国の和紙の産地を巡り、その道を仕事にすると決めたそうです。
現在ロギールさんは、高知県梼原町を拠点に、コウゾやミツマタの原料作りをするかたわら、冬の間は伝統的な和紙づくり、夏になると依頼があった和紙の作品などの制作に取り組んでいます。その合間には、ワークショップを通じて、和紙の魅力を次世代へ伝える活動も行っています。


ロギールさん「いま、和紙は日常生活でほとんど使われておらず、作り手の皆さんも苦しんでいます。それでも、日本では1500年前から、中国では2400年前から和紙が作られていて、その伝統は脈々と受け継がれてきました。
僕が日本で学んだそれらのストーリーを次の世代に渡さないといけないという想いで、ワークショップで和紙の魅力を子どもたちに伝えています。僕はどうやら教えるのが好きみたいだし、オランダ人に日本の伝統を教えてもらうのも、ちょっと面白いでしょ(笑)」
ロギールさんが子どもたちに伝えたいのは、和紙の素晴らしさだけではありません。現代の子どもたちにとって必要なことが、和紙づくりのワークショップに詰まっていると言います。
ロギールさん「今の子どもたちは、スマホやパソコンでの調べ物が得意で、知識もすごいです。でも、知識はすごいけれど、物に“触る”ことは足りていないかもしれません。昔は、襖や障子、灯り、傘など、生活のいたるところで紙が使われていたけど、現代はそれがどんどんなくなってきていますよね。だから、体験するしかないんです。あとは、水を触ることもすごく大事。水を触ることで、水の勉強を無意識にしているんですよ。紙漉きのワークショップでも、実は水を使うところが一番重要なのです」


松屋銀座での紙漉きワークショップでは、和紙の原料を作っている畑を見られるのも、大きな魅力です。子どもたちは、コウゾを直接見て触り、和紙がどんな植物からできているのか実感できるのです。
ロギールさん「松屋銀座にはデザイン性の高いアイテムが並ぶフロアもあり、そういう場所でワークショップを開けるのが素晴らしいです。皆さん、堅苦しくなく、よりリラックスして参加してくれます。親御さんはフロアを歩きながら子どもたちにさまざまな物を見せることができるし、子どもたちはワークショップで作品を作り、原料の畑を見て、水にも触れられる。そうした体験の全てに注目してほしいですね」
ミツバチの蜜源のために作られた屋上の緑化空間が、松屋社員によって育てられている植物をきっかけに、地域やお客様とのつながりを生み、子どもたちへの環境教育にも活用されています。松屋銀座へ訪れた際は、ぜひ屋上まで足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。
銀座の屋上で紙漉き体験 和紙アートづくり

日時:2025年10月19日(日)午前11時30分から、午後2時30分から(各回90分)
場所:松屋銀座屋上
定員:各回16組32名様
対象:5〜12歳のお子様1名と保護者1名の1組2名様
参加費:2,200円
受付:松屋オンラインストアにて9月25日(木)午前11時より予約開始
https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=event
PHOTO/HIKARI TABUCHI TEXT/ARI UCHIDA