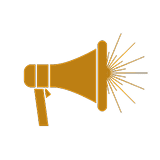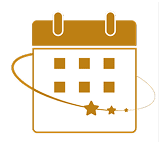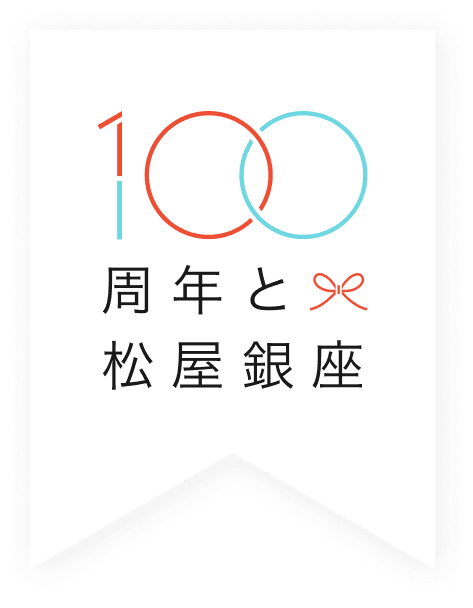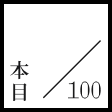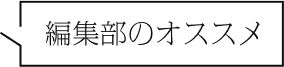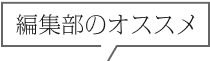銀座の屋上で、年間約2トンものはちみつがとれるのをご存知ですか?そこでとれたはちみつがさまざまな商品となり、自分へのご褒美や素敵な贈り物として届いていく。20年をかけてそれを実現させてきたのが、銀座ミツバチプロジェクト・通称「銀ぱち」と松屋銀座です。今回は、プロジェクトの副理事長である田中淳夫さんと、松屋銀座でこのプロジェクトに携わっている三好拓斗さん、土田祐太さんに、プロジェクト発足からのさまざまなストーリーや、はちみつを使った“銀座の手土産”について語っていただきました。
銀座の屋上で20年育まれた、養蜂プロジェクト「銀ぱち」とは

――銀座ミツバチプロジェクトは、どのように始まったのですか。
田中さん:このプロジェクトは2006年にスタートしました。私が以前役員をしていた、紙パルプ会館の屋上を養蜂家さんにお貸しして、銀座ではちみつを作るという話が持ち上がったんです。当初は、実現したらすごいことだなと思いました。それが二転三転し、養蜂に関して素人だった私たちがやることになったんです。
すると、初年度にも関わらず、桜の香りのはちみつが20kgもとれたんですよ。紙パルプ会館に事務所が入っている松屋銀座さんに「このはちみつを商品に使っていただけないですか?」とお話したら、「面白いですね」と言っていただけて。以来、松屋銀座さんとは20年間一緒に歩んできました。

三好さん:私は2024年に今の部署に異動してきて、松屋銀座の屋上菜園(銀座グリーンプロジェクト)の手入れなどを担当するようになりました。その流れで「銀ぱち」に関わるようになり、先日は採蜜ボランティアにも初めて参加しました。実際に手作業で、巣箱1枚1枚からはちみつをとっていくのを拝見して、そこから年間2トン以上ものはちみつをとるということに、ものすごい労力がかかっていることを実感しました。
土田さん:私は銀座はちみつを使った商品開発に携わっています。プロジェクトが発足した当初は、サステナビリティという言葉は周知されてなかったと思うのですが、近年はこういった切り口の取り組みは重要度が高いですよね。店頭を歩いていても、最近は、お客様の中にもこのプロジェクトに共感していただく方が増えてきたなと感じています。
――銀座はちみつにはどんな特徴があるんですか?
田中さん:銀座にはたくさんの木々が植えられています。春には桜が咲きますし、マロニエ通りにはマロニエ、並木通りのリンデン、そのほかにもさまざまな街路樹が植えられていて、ミツバチがその花々から甘い蜜を集めてきてくれるんです。ハチは3キロ四方を飛べると言われていてここから1.2キロ先には浜離宮がありますし、1.5キロの場所には皇居や日比谷公園があったりと、銀座周辺は緑や花で溢れているんです。
周辺で咲く花々は季節の移ろいとともに変わり、それに伴い、はちみつの香りや味、色も変化していきます。複数の花々の香りや味が、銀座の巣箱にギュッと凝縮するんですね。
三好さん:私自身、銀座という街で、はちみつがとれることに、初めは「えっ」という驚きがありました。でも、実際にはちみつがとれているのを間近で見て、それが松屋銀座で商品として形になる…。そのストーリーや背景も、銀座はちみつの大きな魅力だと思います。

採蜜ボランティアやワークショップを通じて、都会の中で自然を学ぶ

――都会の真ん中でハチを育てることは、難しいことなのでしょうか?
田中さん:1日40万人も集まる銀座でミツバチを飼うことに、当初は「本当に大丈夫なの?」という心配の声がありました。でも実際にはちみつがとれ始めたのを知っていただき、都会でミツバチが集まってくることが自然の循環を生み出すなど、少しずつその意味を理解してもらうことができたんです。そこから、街の皆さんがプロジェクトを支えてくれるようになりました。
銀座は、常に新しいものが入ってくる場所であり、ときには私たちのような奇想天外なことをやらかす人も出てくる街です(笑)。でも、それを受け止めてくれる街なのです。いいものは残るし、街にそぐわないものは見えないフィルターによって自然と消えていく。だからこそ、このプロジェクトを続けるためには、街の皆さんと一緒にその価値を作っていくことが大切です。サステナビリティという言葉がまだない時代に、銀座の皆さんがそれを予感して、街として表現していったんだと思います。

――松屋銀座として、プロジェクトにどのように関わっていますか?
三好さん:蜜源を育てるために、屋上の緑化活動にも力を入れています。屋上の空間は無機質になりがちなんですが、緑豊かな空間にすることでお客様にも注目していただいています。


田中さん:松屋銀座さんには、プロジェクト発足の翌年から一緒にタッグを組んで、銀座グリーンプロジェクトとして緑を育ててもらっていますよね。その一環で、屋上にサツマイモを植えて、芋焼酎を作るプロジェクト「銀座芋人」もあります。11月後半には、サツマイモの大きさを競う「イモリンピック」も行っていて毎年盛り上がります。
三好さん:屋上の植物や菜園などを活用した、さまざまなワークショップにも力を入れています。体験を通して楽しんでいただきながら、プロジェクトの取り組みを知っていただくきっかけになればうれしいですね。これまでは、屋上の植物を使って紙漉(す)きをしたり、機織りのワークショップなども行ってきました。蜜源以外にも、環境に関する教育的な側面でも活用できていると思います。
ワークショップ「銀座ミツバチの蜜蝋でキャンドル作り」

松屋銀座では、銀座ミツバチの蜜蝋を使ったキャンドル作り(ねんど式)のワークショップを開催します。ミツバチが私たちの生活にどう関わっているのかを知ったうえで、銀座はちみつの紹介やミツバチの観察をすることもできます。
日時:2025年8月3日(日)午前11時30分ー/午後2時30分ーの2回開催 ※所要時間 約100分
場所:松屋銀座マロニエ通り館6階セミナールーム
参加費:3,000円
参加条件:松屋の各種カード会員様(ご登録無料のポイントWEB会員様も対象です)
申し込みURL:https://store.matsuya.com/goods/list.html?cid=mrcd
はちみつ作りの背景やストーリーを形に。“銀座の手土産”に込めた想いとは

――はちみつを使った商品開発ではどんなことを意識されていますか?
土田さん:商品開発で気をつけているのは、いつの時期のはちみつを使うのが、商品にとってベストなのかを見極めることです。特に生のはちみつを使う場合は、花の種類や時期によって、はちみつの味わいや香りが変わるので注意が必要です。作り手さんと密にコミュニケーションをとるようにしています。

田中さん:松屋銀座さんのバイヤーさんが、作り手さんにはちみつの味を伝えて、それを一流の技で形にしてもらえるのが、すごく面白いですよね。はちみつが単なる素材ではなく、そこにある背景やストーリーが形になるような感覚です。その作業が20年かけてつながってきたことで、全国にも影響を与えたんじゃないかと思います。
――銀座はちみつを使った商品は具体的にどんなものがあるのでしょうか? おすすめを教えてください。
土田さん:毎年、10種類以上の商品を発売しているのですが、『ラベイユ』さんの「銀座のはちみつ」が定番です。ラベイユさんの瓶にボトリングしたシンプルな商品ですが、ダイレクトにはちみつのおいしさが感じられます。店員さんからも、「銀座のはちみつ」ができた背景などを一緒に伝えていただき好評を得ているようです。
田中さん:こういう商品を手土産に選んでもらえれば、それを渡すときに、背景やストーリーを親しい方や大切な方に伝えることができますよね。そうやって多くの方々に、ミツバチが教えてくれる大切なメッセージが広がってくれたらと思います。

土田さん:今シーズンのイチオシは『KURAKICHI』さんの「KURAKICHIあきたフルーツクッキー缶(松屋銀座100周年記念アソート)」です。松屋銀座の100周年を記念して、限定で作っていただいた商品で、クッキーに銀座はちみつが使用されています。パッケージも手に取るきっかけになりますので、100周年らしくクラシカルで、華やかさのあるデザインにしていただきました。クッキーはハチの巣穴を模したものが2種類入っていて、見た目にも“はちみつ感”を表現してもらっています。特別感や希少性がしっかりと伝わる仕上がりになったと感じています。

今年も「銀座はちみつ」を使った商品が店頭に続々登場予定。オンラインストアでは、銀座文明堂の「銀座の蜂蜜カステラ」や、喜多福の「銀座はちみつ梅」など、全15種を販売中です。
ミツバチがつないだ街と自然の物語を、大切な人への贈りものにぜひ。
松屋オンラインストア:銀座はちみつを使ったスイーツ
https://store.matsuya.com/goods/list.html?cid=fs_sf_honey
PHOTO/HIKARI TABUCHI TEXT/ARI UCHIDA